 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
2010 Dec. カミサンのティータイム: カラスウリ

Photo : Y. Tsukamoto
いいも悪いも おっと 最後にとびだしたのは 占ってみるかい (塚本和江記)
2010 Dec. “ARCHIVES ”2006−2010年に思う
BIRDER誌(文一総合出版)に2006年1月号から登場した”ARCHIVES”の連載が、この12月号で最終回を迎えました。カラー全盛の時代にあって、モノクロ写真のページづくりはどんなものかと思われましたが、誌面のほとんどの写真がカラーだけにモノクロのページがかえって異色の味を出して好評だった?ようです。
 グラビア連載として5年間よくぞ続いたものと、我ながら感心しています。これもひとえにモノクロ写真ファンあってのこと。バード・フォト・アーカイブスに得難い写真をご提供くださり連載を可能にしてくださった生態写真家の皆さまに、この場を借りて心から感謝申しあげます! 写真をご提供下さった方々のお名前をささやかな記録として以下に列記させていただきます。[敬称略:同じ年に複数回掲載の撮影者は(掲載回数)を記入]
5年間という時の流れとその間に掲載された写真の数は、一つ一つの積み重ねの結果ではありますが、その積み重ねがページを構成してきた私にはまた別の意味を持ち、新たな感慨を産む感じがしています。このままではもったいない気がしてきました。そうだ、連載されたものをこのホームページに転載し、“ARCHIVES”を再現できないものだろうか? The Photo 「今月の1枚」のページには、引き続きバード・フォト・アーカイブスにご提供いただいた写真を順次掲載させていただきますので、ご期待ください。モノクロ写真のご提供、或いはモノクロを死蔵されている方への呼びかけなども、どうぞよろしくお願いいたします。(塚本洋三記)  目をつけられたなら 天ぷらかい? (塚本和江記)
Photo : Y. Tsukamoto
2010 Nov. 下村兼史のとそっくりなグラフレックスカメラ登場
野鳥を主とした生態写真の日本の先駆者下村兼史 (1903-1967) が、撮影活動の初期に使っていたカメラにオートグラフレックスがある。その実物らしきを手にしたのは今から5年ほど前、山階鳥類研究所で「下村兼史資料」の整理保存をお手伝いし始めたときのことであった。
段ボール箱に詰まった下村資料とともに出てきた古びた革ケース。この大きさ、もしやあのカメラ? 「おおっ、下村兼史が使っていたオートグラフレックスだ!」 私は一気に昂揚した。 下村資料整理保存プロジェクトの私のボスHさんは、研究者である。冷静そのもの。「塚本さん、そのカメラを下村が使っていたという証拠はあるのですか?」「・・・」返事に窮した。 しかし、である。下村の写真資料の中から出てきたカメラ。しかも、そうザラにあるカメラではない。下村ファンとしては、下村が使っていたカメラそのものであって欲しかった。 ボスのごもっともなご指摘で学者魂の片りんにふれた思いの私。お陰で、正確には“下村が使っていたと思われる”と表現すべきカメラとの出会いが、一層忘れ難いものとなった。 そのカメラ、ちょっとカビのはえたシャッター幕が半開きのままだし、レンズがない。当然、カメラとして機能してはいない。しかし、下村兼史が1920〜30年代に数々の傑作を撮ったのは、私が手に持ったそのオートグラフレックスではあるまいかと想像するだけで、十分に満足であった。 下村が使っていたと思われるR.B. AUTO GRAFLEX の文字がシャッタースピード表に刻まれたそのカメラは、下村兼史資料の一部としてアルミ製のケースに納まって山階鳥類研究所に収蔵されている。 
忘れもしないあの瞬間。日本時間で去る11月11日午前9時4分30秒。私にネットオークションの経験がなかったばっかりに、140ドルで入札していた誰かに恐らく数10秒の差で私の150ドルの入札が間にあわなかったのだ。念願のオートグラフレックスを手に入れることは叶わなかった。
人生初のしかも国際入札でブッツケ本番だったのだから無理もないが、なんとしても惜しい。「最初からムリをしないで。オークションは冷静に、冷静に! 終盤の入札で競り合って熱くなってはいけませんよ、塚本さん!」と、こぞってアドバイスしてくれたネット先輩のBさん、Mさん、Oさん。アメリカのネット市場には結構グラフレックスが出回るらしいから次ぎの機会には・・・、と慰めてくれた。 そうは言われても、アメリカを代表する唯一ともいえる一眼レフ、グラフレックスは、1907年から56年間も作り続けられたと聞く。28種にものぼる機種があるそうなのだ。オートグラフレックスは、その1機種。3×4手札判やそれより大きな4×5判、さらに5×7判があり、それぞれに似て非なる型やシリーズものがあるらしい。私は、下村が使っていたような同じ型のオートグラフレックスはアメリカのネットオークションでもなかなか出ないのだよ〜と、内心ボヤクしかなかった。 その日の夕方、諦めきれない私は、こんな型のカメラが日本でもアメリカでもいいからネットオークションにでていたら教えてくれと、カミさんに“こんな型”をコンピューターの画面上で示してみせようとした。競売品を追ってマウスでたまたまポイントした先の“こんなカメラ”・・・。私は我が目を疑った。それは、山階鳥研に収蔵されているカメラと限りなく 似ている型で、しかもその朝落札しそびれたものよりはるかに状態が良さそうだ。早いもの勝ちの一発即決即売ときた。競争相手はオレしかいない、と妙な錯覚にとらわれた。 うお〜〜、タイヘン・・・。焦る気持ちをおさえてパソコンに向かう。まず「入札」、クリック。「ユーザーIDとパスワード」を(落ち着けっ、急げっ、落ち着いて!と自分に言い聞かせつつ)入力。即「OK」をクリック。数秒遅れで折り返しモニターに出た「入札確認」をクリック。一瞬が過ぎ、入札表示が「終了」に変わる・・・(ドキドキドキ)・・・ 落札したのはオレか?(神様、下村さま〜)。 コンピューターの画面を睨みつつ祈るような気持ちの待ち時間が長かったのかそうでもなかったのか・・・。出たっ!「Mr. Y−塚、あなたが落札しました。CONGRATULATIONS!」のメッセージ。「やったぁ〜!!」 朝のオークション地獄から夕方には極楽へ、なんとラッキーな私。 その晩寝ている間にカリフォルニアから請求書が届いていて、朝起き抜けに、送料込みで400ドルほどの支払い完了。件のイーストマン コダック社製 F4.5の7.5 inch(約190mm)のレンズをつけたR.B.オートグラフレックス1913 レフレックス 3×4判 カメラは、航空便であっという間に、実は待ち遠しい1週間の日々を耐えた私の手元に無事届いたのだった。  改めて憧れのカメラを手にしてみると、カメラには違いないが、“怪物”とでも呼びたいしろもの。これがカメラだと知ってはいても、まずこんなに重くてよいものなのか。“グラ”を目の前にして感無量の私であったが、これをフィールドへ持ち出す勇気が起きないほど、重い。事前に私の腰痛を気遣ってくれたBさんが、言わんこっちゃないでしょと笑っている姿が目に浮かぶ。 とても見つかるまい、万一見つかっても手が届くまいと諦めていた私は、恋人に出会ったかのように “グラ”を眺め、作動する部分を動かしてみたりボデーを撫でてみたり。今、すっかりゴキゲンなのである。さりとて、この物体、これからどうしてくれよう?!(塚本洋三記)
2010 Nov. カミサンのティータイム:じょろうぐも
2010 Oct. カミサンのティータイム:オオカマキリ

センニンソウの ま白きガクで
身を飾らせておくれ この大きなカマで 刈らせておくれ ああ 巨大な♀よ もっと雄大な虫になるために あたしゃ まっぴらごめんだね (塚本和江記)
Photo : Y. Tsukamoto
2010 Oct. 地デジテレビで劣化する日本人の色彩感覚
アナログから地デジへの切り替え日が迫って来る。
便利ならなんでも飛びつく習性を身につけた近代人には、地デジ化は歓迎されるであろう。それはそれで結構である。アナログで充分と考えている人がアナログを選択できなくなるというのは、私たちの生活文化の多様性が失われること。そんな社会に生きたくない人にとっては迷惑なことだ。 多様性には、今話題の生物多様性ばかりでなく、等しく大切な“文化の多様性”がある。それが、私たちの思いとは関わりなしに制限をうけたり失われてしまう時代とはなった。オソロシイことである。 生憎というかタイムリーというか、わが家の古テレビが壊れ、デジタルテレビを購入した。高齢者の仲間入りをした私は懸命にデジタル化に適応しようと日々もがいているが、アナログへの郷愁にも似た気持ちが断ち切れないでいる。新調の地デジテレビながら、ギリギリまでアナログで見ていようという空しくもささやかな抵抗を諦めるつもりはない。  確かに、ハイビジョンデジタルテレビの美しさには、見た最初は私も目を見張った。この世にこんな美しい映像があってよいものかと、驚きと羨望のまなざしで量販店の店頭で棒立ちになってテレビ画面を凝視したものだ。 憂うべきことは、日本人の鋭敏にして雅趣豊かな色彩感覚が地デジによって劣化していくのではなかろうかという点である。ハイビジョンデジタルの“美しい”画像に人は次第に見慣れていく。その感覚が世代の代わるころには、日本人に自然に培われていた色彩感覚が失われる崖っぷちにいたということにならなければよいが。 2010 Sept.カミサンのティータイム:とんがらし 
Photo : Y. Tsukamoto
こんなに小さな身なりして ああ とどのつまり (塚本和江) 2010 Sept. 田中徳太郎の次は、堀内讃位
モノクロ写真の“追っかけ”をしている私にとって、Mさんこと松田道生さんの存在は実に心強い。野鳥の研究、鳥声録音家。彼のブログを一読すれば、会わずしてお人柄がうかがい知れる。田中徳太郎のモノクロ写真の原板の所在をつきとめることができたのも、松田さんの情報が決め手だった。
松田さんご自身のブログ、2010年8月26日の「田中徳太郎を捜せ」(http://syrinxmm.cocolog-nifty.com/syrinx/2010/08/post-4680.html)で、田中徳太郎の思い出にふれ、田中徳太郎の追跡が一件落着したら、「塚本さんの次の指示は“堀内讃位の遺族を探せ”」と結んでいる。 ハテ、私は指示など出した覚えがない? 過日あるお通夜での立ち話で堀内讃位の写真探索を話題にし、私の意をくみとって堀内讃位の大捜索策戦にさっそく一役買ってでてくれたに違いない。私の意をくんでもらえるように話を進めた気もするが・・・。 松田さんはやたらとお忙しい人。「たまたまお仕事の合間にどこかで堀内讃位の匂いがしたら、書きとめておいてくれれば有難いです。」とメールを送るのを忘れなかった。 ところがである。さっそく「堀内讃位の『写真記録日本鳥類狩猟法』と『写真記録日本伝統狩猟法』をお送りしておきました。」とのメールが。 「なにぃ! 送った?」松田さんのフットワークの軽さに目眩がしそうだった。わが家の狭い本棚に収蔵するスペースはない・・・。そんな事情にはお構いなしに、「後著は、重いです。腰を痛めそうですので、ご注意ください。」と。私が肝心の写真集を持っていないことを知ってのご親切に重ねて、腰痛まで気遣ってくれることを忘れなかった。いやはや、いいヤツ(失礼!)だ。  メールが届いた翌日、えびすビールのケース箱に収まった件の本がドンと届いた。久々に手にする堀内讃位(ほりうち・さんみ 1903-1948)の『写真記録日本伝統狩猟法』(株式会社出版科学総合研究所 1984)。ケース入りの重量、4.3kg。 455ページの大著。
2010 Aug.カミサンのティータイム:かぼちゃの花

じつのところ
日のあびかたで 夜の形がきまる ああ かぼちゃ 時にシンデレラの馬車 けど 特別でないカボチャはどうする (塚本和江記)
Photo : Y. Tsukamoto
2010 Aug. 田中徳太郎の原板は健在!!  Mさんからのメールには、ウエブで探し当てたばかりという一つのサイト情報があった。それはJCII フォトサロンが2008年4-5月に開催した田中徳太郎作品展「白鷺」に関してだった。この写真展は私が気付かない内に終わっていたが、事後に同じサイトで知ってはいた。そのことをすっかり失念していた。 それにしても、伊東さんが、お若いころから田中徳太郎の写真材料店をお手伝いし、兄が撮りつづけたフィルムの現像から引き伸ばしまで一手に引き受けるほど写真術に長けていたこと、これ以上ないと思われるほどきちんと原板を整理保管されていたことなどは、まったく天が味方したという他にない。 日本のモノクロ写真時代のほとんどの野鳥生態写真家の原板やプリントは、それらの保管者すら探り当てるのが困難な状態にある現在、田中徳太郎が一件落着したのは、まさに例外中の例外である。兄の田中さんにして、あの妹さんあり。お二人の連携で、撮られた野田の鷺の写真の原板が文化遺産として後世に伝えられることが確実となった事実が、次なる原板追跡目標に向かって私に新たなエネルギーを注入してくるのだった。
先月このページで、埼玉県野田の鷺山で田中徳太郎が撮ったモノクロ写真の原板は、妹さんが持っているのを目撃した人がいるとのSさんの証言が最後だったと書いた。妹さんのお名前も消息も知れないままにそれ以上の手がかりもなく、さすがの私も追跡をあきらめかけていた。
ところがアップした翌7月19日のことだった。Mさんからメールが入る。「いつ何時、ひょんなことで解明できるかもしれません。その日が来ることを祈っております。」と。なんと“その日”が早くも来ることになったとは。以下はその顛末である。 2010 July カミサンのティータイム:びんぼうかずら 
Photo : Y. Tsukamoto
2010 July 浦和学院高校に田中徳太郎のサギの写真が実在している!
かつて特別天然記念物に指定されていた埼玉県野田の鷺山を舞台にサギを撮っていた生態写真家、田中徳太郎の作品は、今日では『しらさぎ』(1970年 講談社)などの写真集で見られるだけになってしまった。と思ってこの何十年か無念に過ごしてきた私だが、梅雨のあいまにムッとする暑さの七夕の日、田中徳太郎のオリジナル写真をついに拝見できる機会を得た。鷺山にほど近い浦和学院高校で。部外者が自由勝手に見ることは叶わないが、私は巡り巡って紹介された同校の理科主任倉成英昭先生に、構内の図書館へご案内していただいたのだった。
 入館して見上げる吹き抜けの壁面にかかっていたのが、私のもっとも好きな1枚――星の軌跡を背景に、モクレンが満開で咲くが如く月明かりに眠っているチュウダイサギ(今でいうダイサギ)の群れ――『月の光』と題されたその幻想的な1枚だった。まず度肝を抜かれた。2m×3mはあろうかと思われる立派な額に納まった超特大の傑作である。2階踊り場から同じ目線でためつすがめつ眺め、こんな“大物”の存在に、ため息さえもらした。 白や赤 ああ (塚本和江記) 2010 June カミサンのティータイム:うめの実 
ぱんぱんな梅の実が
TV CMのなかから 画面の外へ流し眼 うー 青い あの頃 塩分 8% すこーし優しそうに おお写しの梅が (塚本和江記) 2010 June 写真・“写偽”・BPA・ラファエロ
写真とは文字通り“真を写すもの”と思われた時代があった。そのころは、撮影時に露出不足と感知すれば(露出計内蔵カメラなどなかったころの話)勘を頼りに現像時間を“押して”不足を補ったり、引き伸ばしの際に光源からの光を手のひらで遮ってプリントの焼き上がりを加減したり、プリントのキズを極細筆で丹念にスポッティングしたり、などなどの原始的手法での、今でいう加工処理とはいえないほどの、写真術はあった。出来上がったプリントは、“見えた通りに写っている”というのが当たり前というか、“見えたものと違って写っている”などとは疑うことすらなかった。写真とはそんなものだった。
今日、コンピューターが一般に行きわたり、デジタルカメラがフィルムカメラに取って代わった。デジカメ撮影が誰にでも簡単容易にできるようになった。一方で、どこかがおかしくなってきた。原因は、デジタル画像は画像ソフトを使ってコンピューター上で簡単に加工処理が可能となるからだ。 かくいう私も、画像ソフトを使う。“写偽のスケール”の一端に厳密にはひっかかりそうな加工を、してよいものか否かで苦慮することもある。もうちょっと、もう少しならいいだろ、という加工への誘惑と自己へのアマエは、常に感じる。画像処理ソフトに一度手をそめると、加工技術に汚染されていく己を意識する。麻薬のようなものに違いないと感じている。それだけに、自制心と自信が必要だ。  先日、ラファエロの傑作「大公の聖母」が新聞ネタになった。画の背景の黒色は後年別人によって加筆されたことが、赤外線分析や断層撮影の科学調査で判明したという。背景にはもともとラファエロによる建築物や山河らしき風景が描かれているというのだ。名画とは? 名画の質をどう捉えるのか? 原画の復元を試みるべきか? 科学の力は、分からなかったものを明らかにする一方で、頭の痛い課題を現代に投げかける。
Photo : Y. Tsukamoto
2010 May カミサンのティータイム:おおでまり
 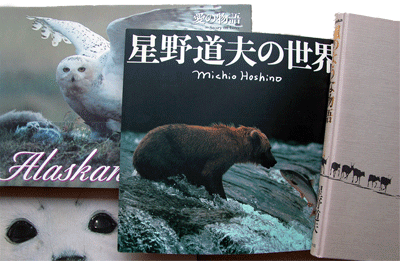
ふりむいたら 5つ
手毬唄でコロンと遊ぶ あたり一面 おおでまり ぬりかえられる思い出は タイムマシーンの花よ (塚本和江記)
Photo : Y. Tsukamoto
2010 May 星野直子講演会「星野道夫と見た風景」 連休明けに、小人数でスライドを観ながらのぜいたくな講演会に参加することができた。幸運だったとしか言いようがない。写真集で親しんだ星野道夫さんの写真が次々とスクリーンに映し出され、撮影にまつわる逸話が星野直子夫人の静かな語り口で披露されたのである。 アラスカの野生を、胸に迫る写真と精緻な筆で表現し続けた自然写真家文筆家、星野道夫との出会いは、『Alaska風のような物語』(小学館 1991年)だった。背表紙のタイトルに惹かれるように本屋の棚から取り出してパラパラッとページをめくり、即決で買ってしまったその本。アラスカを語る文章は、1-2行のキャプションでさえも説得力があった。撮られた野生動物の姿には、人の心に訴える“なにか”が感じられた。 星野道夫の写真の中でも、桁外れに広漠たる原始アラスカを舞台に、ヒグマだっ、カリブーだっ、クロクマだっ、ヘラジカだっ、ホッキョクグマだっ、鯨だっ、アザラシだっ、なにか動物が画面のどこかにポツンと構図されている写真に逢うたびに、特に私はシビレルのだ。 普段は銃を持ち歩かなかったという。大型の野生動物にでっくわす機会の多いフィールドに丸腰でただ一人、そりゃタイヘンなことなのだと想像しつつも、ライフルを持った人間を動物たちが警戒してシャッターチャンスを逃すからだと、凡人は思う。星野の考えは、銃を持ってしまうと自身が安心してしまって、畏怖の念や五感を働かせる意識が薄れるから、だ。凡人は、自身と星野との隔たり、自然に対する認識のなんたる違いかを思い知らされる。 「どうしてヒグマにあんなに近づいて撮れるのだ?」とアラスカの友人に聞かれて、星野は「ヒグマと一緒に呼吸することだよ」と語っていたという。 アラスカの大自然とそこに棲む野生動物たちの写真を撮るのに、「夫は場所を選び、時間をかける。待つ。待ち続ける。ず〜っとひたすら待つ時間が、ほとんど。写真を撮るのはほんのわずか」だったそうである。 写真集でお馴染みのヒグマとサケの写真がスクリーンに映る。清流に踏み込んでサケを狙っている若いヒグマのまさに鼻っ先に、サケがジャンプした瞬間のシャッター。 写真がどれであれ、“その後どうなったか”はもう二度と星野さんに問うことは叶わない。あの事実を受け入れねばならないのだ。星野道夫は、1996年、カムチャツカで取材中にヒグマに襲われて急逝された。 星野道夫の写真も文筆も、アノ時までに残されているもの以上に増えることはない。しかし、充分過ぎるものを遺して逝った。改めて星野道夫の人間と作品の大きさを思う。その星野道夫ワールドを、星野直子夫人は後進にまっすぐに伝え広める活動を続けている。心からのエールを送りたい。(塚本洋三記)  2010 Apr. カミさんのティータイム:さくら
大きいような 小さいような
さくらのはなびらの丘が ふるふる 揺れる フロントガラスに張り付いた一枚が どんどん よんで まるごと くるまごと 一台のさくら 桜の花は いいも悪いも 隠す スーハー呼吸するピンク玉 (塚本和江記)
Photo : Y. Tsukamoto
2010 Apr. 山階鳥類研究所所蔵 下村兼史資料の報告文
下村兼史(1903−1967)は、日本で野鳥を主とした生態写真の草分けである。野鳥の写真や映画を撮ってそれを生涯の仕事にしようなどと誰も考えなかった時代に、そのフロンティアを自ら拓いて歩み通した男。
下村の不屈の生き様には驚かされる。下村を支えたのは、野鳥や自然への愛情や情熱であり、レンズを通して野生を乾板やフィルムに記録するという一徹な姿勢にあったのではなかろうか。 カメラセンスは抜群。今日発達した高精度のカメラにくらべればおよそプリミティブな機材で、過酷とも思える撮影条件のなか、味のある作品を数多く残している。 下村兼史が生涯撮り続けた乾板、ネガ、プリントなど写真資料のほとんどが、下村の没後ご遺族から財団法人山階鳥類研究所へ寄贈された。2005年になって、世界に2つとないお宝資料の整理保存作業が進められることになった。現場責任者は私がさせていただくことになり、ほぼ4年をかけて1万点を越える写真および文字資料の整理保存作業が完了した。 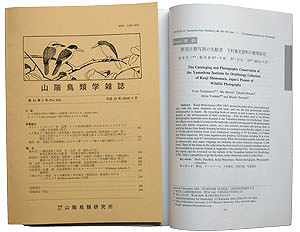 この度、下村兼史資料11,304点の整理保存に関する報告文が掲載された「山階鳥類学雑誌」第41巻2号が発刊された。下村プロジェクトチーム5人(現場で私と二人三脚で的確に作業を進めた廣田美枝、私の直属のボスで同研究所広報主任の平岡 考、画像保存で日本のトップランナーの東京工芸大学芸術学部写真学科吉田 成教授、同研究所自然誌研究室の室長鶴見みや古の皆さんと、下村作業を担当するために与えられた客員研究員の肩書きの私の5人)の共著であるが、作業開始から報告文の掲載まで、ほんとうに多くの方々のご指導に支えられて完了することができた。謝辞に述べられているが、この場をもお借りして心からのお礼を申しあげたい。 掲載誌の性格上、報告文はカターイ内容表現となっているが、下村作品を含めた一般向けの資料紹介は、山階鳥類研究所のウエブサイトに下村兼史のサイトがあるので、こちらをお楽しみいただきたいと思う。同サイトは、下村チームメンバーからの口やかましい注文を受け一手に制作を担当した当時同研究所広報室の原田亮子さんの力作である。併せてお礼申しあげたい。 なお、こと下村兼史資料の利用についてのご質問・お問い合せは、同研究所の下村資料提供窓口となっている(有)バード・フォト・アーカイブスへ直接ご連絡ください。 2010 Mar.カミさんのティータイム: 体調をかなり悪くして、お休みを (塚本和江記)  2010 Mar. 便利さを求めて、失うもの
締め切りが目前に迫ってくるまで、雑誌などの原稿書きや写真データの準備に手がつかない私。原稿などの郵送にかかる日時が気になるし、いよいよ時間がなくなると編集部へ車を飛ばして届けることになる。その時間が実にもったいない。しかも、運転には危険がともなう。深夜だから人はいないとタカをくくって飛ばすと、深夜だから車はこないと決めつける人が道路を悠然と横切っていて、愕然とさせられる。そんなにまでしなくたって、締め切りに早め早めに対処すればよいとは分かっているが、そうはいかないのが人間である。
ところが、この数年ほど、コンピューターのお陰でそのあたりが楽で便利になった。以前は、メールで送られないような“重い”データは、リムーバブルディスクにいれて編集部へ持ち込んだ。そんな大容量ファイルをネットを通じてしかもタダで送れることがわかった。以前は紙焼きで送られてきた校正もPDFなるものでメールされるようになって、仕方なく私もソフトを購入し、PDF上で修正して送り返す。 実に便利になったものだ。原稿さえ書き終えれば、即編集子宛て送信し、イッチョ上がりである。なにもかも、座っているだけで総ての作業が片付いてしまう。さっすがぁ、コンピューター様々である。
Photo : Y. Tsukamoto
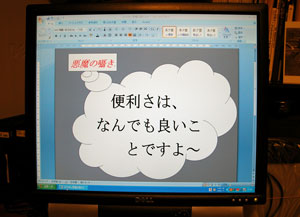 こうして便利な数ヶ月、1年が経ってみて、ふと、なにか足らんぞと思いつく。なんだろ? 以前は当たり前だったことが、脱落してしまっていたのだ。編集子に面と向かうことがない。挨拶がわりの最近の情報交換がない。立ち話での言い訳やら、ちょっとしたムダ話がない。じゃ今日はちょっと一杯やりましょうかの、貴重な打ち合わせ時間となるお酒タイムまでが消えていた。 便利さは、便利な反面、なにか大切なものを私たちから奪ってしまう。現代社会生活の悪魔。意識してうまく悪魔とつきあわないと、気がつけば取り返しのつかない人間不在の社会生活を送るハメになる。それはイヤだっ。(塚本洋三記) 2010 Feb.カミさんのティータイム: 
なんだか笑っちゃうほどの
あおぞらに 黄色の花が踊る “格調” と “お色気”の 混じり合った美味なる香り 宙にただよう ぷっ ぷっ ぷっ 天にむかって たれよ 放てよ 神様の お・な・ら (塚本和江記)
Photo : Y. Tsukamoto
2010 Feb. 紅梅、バレンタイン、そして生命
紅梅が、今年は早くも1月22日に一輪咲いた。翌日三輪となった。2月に入って満開。母が遺していった盆栽だが、ベランダで水だけあげてほったらかしておいても、毎年よく咲いてくれる。芳香が空気を和ます。
紅梅の咲くころは、なにかと生命が絡む。  3年前のバレンタインデーにはカミさんが脳出血で倒れて生死をさまよった。鳥仲間と一杯やってゴキゲンな帰宅途中のできごとで、いささか気まずかった思いは今もこころの片隅に残っている。それはそうなのだ。顔と言えば顔がムンクのように左下に流れて崩れ、右半身は不随。なにか訴えているらしいが言葉にならない唸り声と涎がでるばかり。これが愛するカミさんかと、ベッドにいた“異人さん”を一見し恐怖の念さえ覚えたのだった。 今年の“鬼門バレンタインデー”はちょっと早目にやってきた。仏壇の前に持ち込んだ紅梅の香が室内に漂う3日の朝、姉の緊急手術の連絡が入った。体調の落ちていたカミさんの面倒みるどころではなくなった。駆けつけた病院の担当外科医との手術直前の会話は、真剣なものだった。 常々考えている生命という命題に、姉の緊急手術で思わぬ応用問題を突きつけられた形であった。手術は成功したが、命の尊厳とは? 人の幸せとは?の答えは、神のみぞ知る。現実の選択に運命を感じた。
ろうばい
2010 Jan. カミさんのティータイム: まつ
あっち こっちに
伸びる 松葉よ 今年はいい運? 悪い運? こよりを何千枚とかけて 占ってみよう うえ した 右斜め45度 初日の出に (塚本和江記) 
Photo : Y. Tsukamoto
2010 Jan. 新年明けまして 
虎年年頭に気になるのは、トラぬタヌキのジャンボ宝くじ。クジ運のまったくない私とカミさんのコンビでは、抽選結果を気にしたところで知れている。だが、手元資金だけではとても足りない金の要る仕事をなんとか近年中に実現したいので、見えている結果でも気になるのが人情というもの・・・。
まじめに気になるのが日本経済の雲行き。鳩山内閣、景気よく名目3%の国内総生産成長率を旧年末にぶち上げた。2020年までの目標というが、バブル崩壊後の1994年の4%に次ぐ高率。「新たな政権の実行力が試される時だ。何としてもやりきるという思いだ」と、鳩山首相は記者会見で述べられたそうだ。やりきってもらうしかあるまい。
おめでとうございます。
本年もバード・フォト・アーカイブスの活動を旧年にも増して どうぞよろしくお願い申しあげます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright, 2005- Bird Photo Archives All Rights Reserved. |